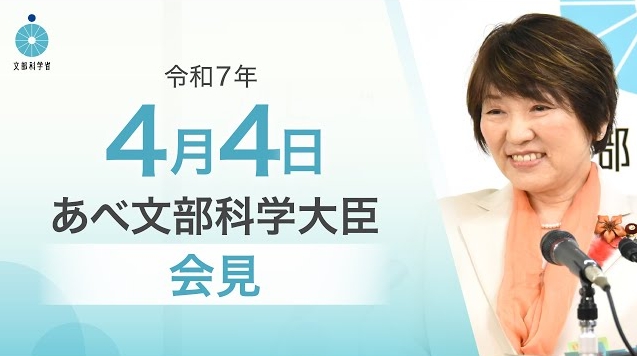- 現在位置
- トップ > 会見・報道・お知らせ > 大臣記者会見等 > あべ俊子 文部科学大臣の会見 > あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年4月4日)
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年4月4日)
令和7年4月4日(金曜日)
教育、科学技術・学術
キーワード
海洋研究開発機構の視察、進学動向が変化する中での短期大学の在り方、障害がある生徒の受験・入学に関する適切な対応、若年層の薬物乱用防止の推進
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年4月4日(金曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年4月4日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
大臣)
冒頭、私からは1件でございます。本日、海洋研究開発機構、JAMSTECでございますが、横須賀本部を視察してまいりました。海底広域研究船「かいめい」を視察するとともに、海洋科学技術館におきまして有人の潜水調査船「しんかい6500」、北極域研究船「みらいⅡ」等について説明を聞きました。特に、「しんかい6500」等が行う深海の調査が魅力的であると感じまして、それを支える船舶などのプラットフォームを用いました深海を含む海洋における研究開発の重要性を実感させていただきました。今回の視察を踏まえまして、深海を含む海域地震発生帯の研究、また北極域をはじめとした気候変動予測研究など、研究船等を活用いたしました海洋科学技術の研究開発の推進に、引き続き取り組んでまいりたいというふうに思います。以上でございます。
記者)
短大の関係でお聞きしたいのですけれども、最近、少子化と4年生大学志向が影響していると思うのですけれども、短大の閉校が進んでおりますけれども、現状、大臣はどんなふうに御覧になっているのかと、今後の短大の果たすべき役割についてお考えを聞かせてください。
大臣)
近年、進学動向の変化に伴いまして、多くの短期大学が4年制大学への転換、また学生募集を停止している状況にございます。一方で、短期大学は、入学者のうち7割が短期大学と同じ都道府県内に所在する高等学校等の卒業生でございまして、地域、地方を支えるエッセンシャル・ワーカーなどの専門職業人材を育成する役割を担っているところでございます。短期大学は、引き続きその役割を果たしていくためには各大学において社会変化、また地域のニーズを踏まえた改革を進めていくこととともに、他の高等教育機関との連携も進めていくことが重要でございまして、文部科学省といたしましても私立大学等経常費補助金などにおきまして将来を見据えたチャレンジ、さらには経営改革等の取組を支援してまいりたいというふうに思っております。
記者)
香川県で電動車椅子を使う男子中学生が県内の私立の高校と直接対話する機会もないまま、設備面などを理由に入学を断られた問題について3点お尋ねさせていただきます。まず、改正障害者差別解消法に基づいて文科省を定めている指針では、障害のある方との対話を通じて相互理解を深め、対応策を検討することが求められていますが、今回の件では直接対応する機会が設けられていませんでした。この答えの大臣の見解をお聞かせください。2点目として、この生徒が県内の私立高校を腕試しで受験した際に、私立高校との交渉にあたっていた中学の校長から「合格しても入学しない」との確約を求められていたとのことですが、適切な対応だったと考えられるか、このことへの見解も教えてください。最後に、今回の件は建設的対話の機会が設けられず、文科省が示している対応指針が現場に十分に浸透していないのではないかということが伺える事案かと思います。今後、どのように教育現場に周知徹底を図っていくかのお考えを教えてください。
大臣)
ご指摘の報道は承知をしておりまして、詳細な事実関係、背景などを承知しておりませんので、個別のコメントは差し控えさせていただきたいとは思います。その上で、一般論として申し上げれば、障害があることを理由として、具体的な場面や状況に応じた検討を行うことなく受験、入学等を拒むことは、不当な差別的取扱いに該当しうると考えられまして、関係者におきましては当事者に判断の理由を丁寧に説明をし、適切に対応することが重要でございます。本件につきましては、香川県知事から、状況を確認した上で、必要な対応をしていきたい、旨の発言がされているものと承知しておりまして、文部科学省としてもその対応を注視してまいりたいというふうに思います。さらに、文科省としての令和5年の12月でございますが、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を改正いたしまして、その趣旨につきましては各都道府県等に通知を行っていますとともに、各種会議等を通じまして周知を図っているところでございます。また、今年の本年2月には、独立行政法人教職員支援機構と連携をさせていただいた上で、小学校・中学校等の教職員を主な対象といたしまして、合理的配慮の提供に関する基本的な考え方等をまとめた研修動画を公表させていただきました。この中におきましては、合理的配慮の提供にあたりまして建設的な対話、これを通じまして相互理解を深めていきながらともに対応案を検討していくことがまさに重要であるということを私ども言及をしているところでございまして、引き続き、こうした内容の周知徹底に努めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
記者)
昨日、4月3日に公表された警察庁の統計、令和6年における組織犯罪の情勢の中で2024年に大麻で摘発された人のうちに20代以下が1,128人の約2割を占めていて、うち高校生が206人、中学生が26人となっておりました。介護の開始年齢も使用開始年齢10代が過半数を占める調査結果もある中で若年化が懸念されている状況であるのですけれども、これに対する大臣の説明をお聞かせいただければと思います。
大臣)
昨年の大麻事犯におきまして、おっしゃるように検挙された中学生の数、過去最多となったことに対しては大変憂慮をしているところでございまして、学校においては警察職員や学校薬剤師などの外部講師も活用した薬物乱用防止に関する教育が行われているところで、令和5年の薬物乱用防止教室開催率でございますが、小学校で79.4%、中学校で90%、高校で87%という調査がされておりますが、加えまして文部科学省としては、若者の医薬品の過量服薬が増えている状況も受けまして、薬物乱用の危険性、さらには有害性について本年の1月からSNSで発信を始めたところでございまして、今後もSNSなどの活用も含めまして、薬物乱用防止に関する教育の充実、しっかり取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございます。
記者)
今おっしゃった薬物乱用防止教育、こちらの中でいわゆる「ダメ。ゼッタイ。」と言われるような危険性を強調した内容になっているかと思うのですけれども、これに対してむしろ相談や治療につなげる敷居を高くしてしまって依存症への偏見を高めるのではないかというような、いわゆる依存症治療に関わる専門家からの指摘もあります。こうした指摘を踏まえた上で、乱用防止教育のあり方についてはどのようにお考えなのか、合わせて聞かせていただければと思います。
大臣)
詳細に関しては事務方のほうに問い合わせていただければと思います。
(了)
お問合せ先
大臣官房総務課広報室